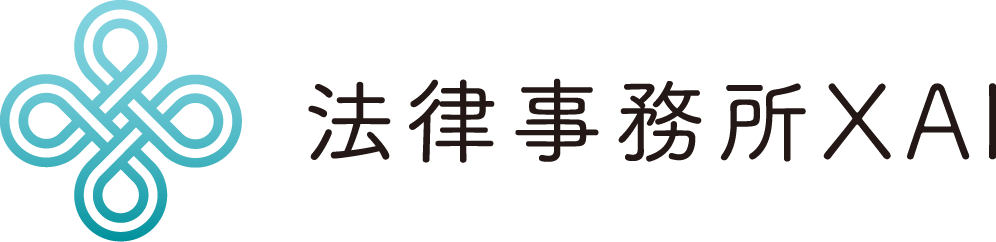Consultation & Solutions
Consultation & Solutions
ご相談・解決事例
法律事務所XAIにおいては、個人の方から事業者まで幅広くご相談をお受けしております。
相談者の方のご意向を踏まえつつ、法的知識やノウハウによって、目指したいゴールへ向かうことを、効果的に支援させていただいています。
このページでは事案のイメージを持っていただくために匿名化したケースをご紹介します。
個人向け
遺産分割についてのケース
ご相談内容
幼い頃に両親が離婚して私は母方に引き取られ、父とはその後縁がなかったのですが、どうも最近父が亡くなったらしく、急にその配偶者の方から連絡が来ました。
「財産はなく借入のみだから相続を放棄してほしい」と言われたのですが、その通りにして良いのでしょうか。
解決アプローチ
本件では弁護士が遺産の開示を正式に申し入れて、その内容の聞き取りを行ったところ、確かに借入はあるものの、それ以上に財産があることが分かりました。
また弊所で独自に銀行や市役所への紹介を行うことで、開示されていない財産をあぶり出すことにも成功し、最終的には遺産分割調停で公平な遺産分割の実現に漕ぎ着けました。
XAIからのメッセージ
相手側から言われた「借入のみ」という話、その真偽をどのように見極めればいいのか、悩ましいところですよね。
しばらく縁がなかった家族の最近の暮らしぶりはわかるはずもなく、相手との間に大きな情報格差がある状況からのスタートでした。
弁護士の介入や調査によって、徐々に実情が判明し、公平な遺産分割が行える状況に辿り着けたのは良かったと思います。
後見に関するケース
ご相談内容
父が金融機関から後見人をつけてもらえないともう取引ができないと言われてしまい、どうしようか悩んでいます。
裁判所に相談に行ったところ、それなりに財産もあるので専門職が後見人に就任することになると言われたのですが、見知らぬ専門家の方が父の財産を管理するとなると、家族の方は不安もあります。どのようにしたら良いでしょうか。
解決アプローチ
不動産の売買などが予定されていたところ、見知らぬ後見人の就任をご家族が恐れているケースでした。実際にご本人と話をしてみると、確かに物忘れや言い間違いはあるものの考えや意思の表明はできる方であり、かかりつけの医師にも意見を確認したところ、やはり後見は時期尚早ではないかという結論に至り、銀行担当者にもその事実を伝えました。
その結果、銀行さんが前言を撤回してきました。今後後見が必要となった場合も、ご家族と弊所で複数後見人の申し立てをすることによって、ご本人の意向に沿った財産管理ができ形を目指そうということになっています。
XAIからのメッセージ
後見制度は、民間では少々濫用気味の傾向があって、福祉施設や金融機関がやたらに後見を進めてくるということがあるようで・・・・申立を受けた裁判所の方でも「このケース、本当に後見が必要なのか?」と首を捻ることも少なくないそうです。そして後見人が一度選任されると基本的に変更がなく、費用も継続的に発生するため、そのタイミングについてはきちんと見極めたいところです。
なお、裁判所は事前に関与している弁護士がいて、申請時にその人を希望する旨が申し添えられていて、その意見を基本的に尊重してくれる運用になっていますので、申し立て以前から弁護士と擦り合わせておくことが実際的にはとても大事なノウハウです。ぜひこのことは知っておいてくださいね。
終活についてのケース
ご相談内容
私はいわゆる独居高齢者で、配偶者も亡くなり子もいません。親戚は数名いますが、遠方に住んでいるのであまり交流もない状況です。
私は今はそれなりに健康なので良いのですが、今後、認知症になったりして施設に入ったりする場合には身元を保証してくれる人もおらずどうしようかと思っています。
また遺産については相続する人もいないので、慈善団体というに寄付したいと考えているのですがどのようにすれば良いでしょうか。
解決アプローチ
①ご自身が生きている間のことと、②ご自身が亡くなった後のことに分けて、何が困るのかについて検討をしていきました。
まずは認知症等で自分一人での財産管理が危うくなってきた場合の準備をしておきたいということでしたので、財産の棚卸をしてリストを作り、弊所と任意後見契約を締結したり、終末期医療に関する意向表明書を作成することにしました。弊所とご親戚で役割分担や事前の費用の手当をすることを前提として、ご親族に身元引受人をお願いすることもできました。
お亡くなりになった場合の死後事務についても、まずはご本人の意向をリストアップして弊所でお引き受けするとともに、ご希望の慈善団体に連絡をし、遺産の寄付の条件について事前調整を行い、その意向に沿った公正証書遺言も作成することにしました。
XAIからのメッセージ
社会問題にもなっている切実なご相談でしたので、ご提供できる法的サービスを一つ一つご説明し、ニーズに合う形で組み立てることによってサービスを提供したケースでした。
親戚の方も「身元引受人」ということで丸投げされると受けられないが、住所地近くでまずは弊所が対応し親族でないとできない役割についてのみ引き受けるということや、費用については本人が負担することが確実な形をとることによって、お引き受けを承諾していただくことができました。
死後事務についても、ご希望の形で財産処分をするためには生前に行っておくべきことが多いケースでもあり、丁寧にアレンジさせていただきました。
法人向け
債権回収、契約解除についてのケース
ご相談内容
取引先に多額の売掛金がありますが、何度請求をしても払ってくれないばかりか、支払う代わりにあれをしろ、これをしろと、かえってサービスを要求されたりしている状況です。
いかにも不当なケースだと思いますが、どうにかしてもらえないでしょうか。
解決アプローチ
弁護士が介入して、依頼者に代金の請求権があることを説明し「一定期間内に支払をしないないなら法的手段を取る」とハッキリ伝えたことで、相手が交渉のテーブルについて来ました。相手方もサービスに対する不満など色々と言い分はあるようでしたが、すでに提供した業務の代金ですから「支払ってもらわなければ裁判にするしかない」と伝えたことで、最終的には支払いを受けることができました。
また、引き続いての取引関係を持つことも依頼者にとって不利益が大きいとの判断もあり、契約解除の通知も弁護士より書面で送ることになりました。
XAIからのメッセージ
弊所に相談に来る方は「いい人」が多いのですが、その分、クライアントに依存されて、それが負担になるという悩みを抱えているケースも少なくないように思います。
そういったケースにおいては、外部からの客観的な目線での介入が有効であり、「取引の基本的なルールとはこういうものですよ」「一線を越えると裁判などの深刻な事態になりますよ」とハッキリ伝えることもさせていただいています。
関係のバランスが取れればそのまま取引を続けることもできますし、一方でそれが難しそうな場合には、相談者がいつまでもその犠牲になってしまうこともあるので、関係を解消するのも一手だとお伝えしています。
労働問題についてのケース
ご相談内容
弊所のある従業員が不正事件を起こして、会社の資金を横領したようです。
ただ明白な証拠があるわけでもないため、どのように扱ったらいいかわかりません。
名誉毀損だと言われる可能性もあるようにも思えるのですが、どうするのが良いのでしょうか。
解決アプローチ
まずはできるだけの証拠の確保が必要なところ、他の従業員からの聞き取りなどによって、できるだけの証拠収集を行いました。
その上でご本人にその事実をぶつけたところ、当初ごまかされたのですが、複数の証言の存在を仄めかしたところ、最終的に認めるに至りました。
また事業所内の混乱こそが依頼者が一番困ることであるところ、刑事告訴等をしない代わりに分割で返金して穏便に退職してほしいと伝えたところ、一度回答を留保されるも、当方からそれなりに譲歩した返済や退職についての条件を提示したところ応じてもらうことができました。
XAIからのメッセージ
法律の世界では証拠の有無が非常に重要ですが、必ずしも全てを確保できるものではありません。ある程度のところまで確保したら、あとは枠組みを作って交渉でまとめる方向へと決断すること、これも重要なスキルになってきます。
また依頼者側のメリット・デメリットを整理した上で、こちらにも利があり、それでいて相手側も応じたくなる示談案設計することも弁護士の腕の見せ所であるといえます。展開が読めない交渉でありましたが、無事ゴールに辿り着けて良かったです。
事業再生・破産についてのケース
ご相談内容
コロナによる経営環境の激変もあって、自社もグループ会社も赤字経営を脱することが出来ないままにいます。
据え置きになっている銀行借入の返済もそろそろ再開する予定であり、資金繰りが相当に厳しい状況になっているのですが、何か打ち手はあるでしょうか。
解決アプローチ
収益構造や財務状況の推移を確認しつつ、今後の経営方針について対話したところ、黒字化に向けて取れるアクションはあるものの、借入金の返済負担があまりに重すぎるということがわかりました。
そこで弊所のM&Aアドバイザーなどの人脈なども駆使し、黒字化しうる事業については切り出して事業譲渡を行い、その対価をもって各社の法的整理を行うこととしました。金融機関各社に対しては経営者保証ガイドラインによる私的整理を申し入れたことで、経営者個人は破産を回避することもでき、現在は関連業界で新たなビジネスの立ち上げの準備を行っている状況です。
XAIからのメッセージ
手を尽くせば事業の黒字化はできるものの、あまりに大きな債務を抱えている状態では、経営者が事業革新に向けたモチベーションを持つことは難しく、その場合にはリスケジュールを繰り返すのではなくて、なんらかの方法で過剰債務の圧縮をすべきであると言えます。
そのためには民事再生による法的整理という方法がありますし、事業再生ガイドラインによる私的整理も広く使われるようになってきています。
お気軽にお問い合わせください
ご返答は平日10:00~17:00内での対応となります。
※メール受付は24時間365日しております。
お問い合わせいただいてから、通常3営業日以内にメールまたは、お電話、その他ご希望の方法にてご連絡させていただきます。
なお、お問い合わせ内容によっては、ご返答しかねる場合もあることについては事前にご承知おきください。