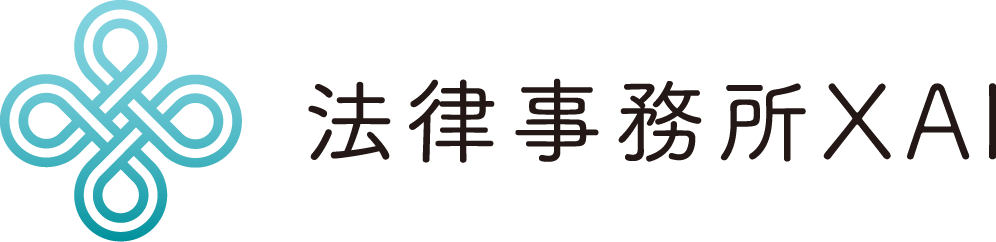Profile
最首克也について
もともと科学好きだった少年が、東大の物理学科を卒業したところから、公認会計士のキャリアを経て、どうして弁護士になったのか?(さらにどうしてコーチやカウンセラーのバックグラウンドがあるのか?)も含めた、「彼」の詳しすぎるプロフィールをご紹介します。
概要
経歴
1980 千葉県いすみ市で誕生、3人兄弟の一番上
地元の小中学校を経て、県立長生高校の理数科に通う
1999 受験仲間に恵まれたおかげで東大の理科一類に入学
2004 東京大学工学部(応用物理学科)を卒業
会計士試験に合格して、監査法人双研社(現:ふじみ監査法人)に入所
監査部門を経て、研究開発(R&D)部門の責任者に
2010 独立してコンサルティング事業をスタート
並行してロースクールへ入学して法律の学習を始める
2018 法科大学院(成蹊大学)を修了、予備試験・司法試験に合格し、
最高裁判所所属の司法修習生(72期・宇都宮修習)となる
2020 弁護士登録後、都内法律事務所でしばらく勤務したのち独立
2022 東京・日本橋から宇都宮に事務所を移転、法律事務所XAIに改称
資格
所属
日本弁護士会連合会 高齢者・障害者権利支援センター
栃木県弁護士会 高齢者・障害者支援センター副委員長
日本公認会計士協会 ITアシュアランス専門委員会(-2015)
栃木県公認会計士協会 県包括外部監査等担当
講演等
三菱UFJ信託銀行、大和証券、帝国データバンク、宝印刷、オービック、OBC、TAC、アビタス、システム監査学会、CSAジャパン、宇都宮大学等にて講演
「米国のe-ディスカバリー(電子証拠開示)制度への対応」「GDPR等、国際的個人データ保護法への対応」「マイナンバー制度とシステム監査の役割」「日米へのIFRS導入の流れを読む」「受託業務に係る内部統制の保証報告書について」「IFRS適用に向けた論点と実務上のポイント」「財務報告はどう変わるか? -海外の開示事例を踏まえて-」等をテーマに
彼がいままでどのように考え、学び、仕事をしてきたか、あるいは、今どんなことを考え活動しているのか、時系列に沿ってエピソードとともにご紹介いたします。

1. 技を極めるのが好きな科学少年
彼はいわゆる「科学好きの少年」で、小さい頃は車いすの天才物理学者「スティーブン・ホーキング博士」に憧れたり、「Newton」という科学誌でその宇宙論に触れて「自分が住んでる宇宙の姿とか、それを成り立たせている法則ってこういうのなのか!」とワクワクしている子供でした。パズルとかクイズとか推理小説とかも好きだったので、「謎解き」みたいなものが好きなんでしょうね。
進学校に進んだ高校生時代には、変わった先生にもたくさん出会い、また「ドラゴン桜」ばりに熱く指導してくれる地元の神童と仲良くなり、「学ぶこと」の深みにハマっていきました。ある先生のセリフ、「数学はエレガントに解かなければならない」はツボにハマったようで、本気でそれを追っかけたりもしていた青春時代でした。この頃から「技を極める」みたいなことが好きだったように思います。

2. 燃え尽きてピボットした大学時代
しかしその後の東大時代、入学したはいいものの、しばらくは勉強のモチベーションを失ってしまっていたのですね。慣れない東京での一人暮らしに落ち着かなかったり、それでいて東大の授業は難しいし、周りはやたらに天才だらけ・・・受験で燃え尽きた感じもあってか、どうにも気分が乗らない数年間でした。
それで現実逃避的なところもあった気がするのですが、日中から授業をサボってサークル活動で体を動かしていて、そのままキャプテンになって運営に没頭していたりしました。で、やってみたらこれはこれで追求したくなるというか、どうやったら組織運営ってうまくいくんだろう、みたいなことに興味が湧いて、人や組織に関わる仕事に興味を持つようになります。
理系から公認会計士試験を受けたのは、このことが原因ですね。
学業が不完全燃焼になっていたのでエネルギーも有り余っていて、卒業年次には資格予備校とのダブルスクールを始めて、1年留年して経済学部や教養学部の授業に潜り込んで過ごしていました。この頃はたくさん本も読んだし、新しい分野の勉強をすることができたんですよね。

3. 情報技術系会計士としてデビュー!
そんな経緯を経て、研究者ではなく会計士としてキャリアをスタートするのですが、業界では理系出身は珍しい一方で、当時の会計士業界は情報技術(IT)を活用したデータ処理が現場を席巻し始めた頃でもあったので(今の生成AIブームみたいに)、データベース、ネットワーク、セキュリティといった情報技術分野を専門にするようになっていきました。
とはいえ彼が大学でやっていたのはコテコテの物理学で情報処理の授業を多少受けた程度だったので、この頃は技術者向けのトレーニングに通って、実機をいじったり技術系の書籍を読んだりして地道に知識をつけていきました。その道標として、この頃はやたら技術者系の試験を受けていました。
そんな道を歩いた結果、監査法人では研究開発部門の責任者として、先端分野を一手に引き受けさせてもえるようになって来て、公認会計士協会のIT分野の専門委員になったり、学会に登壇させてもらえるようになり、セキュリティの業界団体で文献翻訳に加わったりするようになりました。調査研究で海外に行くこともできたりして、さまざまな出会いに興奮しっぱなしだった気がします。

4. 充実の専門職研究者ライフ
ちなみに彼が監査法人に入った2000年代前半というのは、小泉さんが総理、竹中さんが金融担当大臣という構造改革時代で、金融業界のグローバリゼーションを背景に「金融・会計ビッグバン」と言われる会計士業界のルールの大転換が起こっていた時代でした。
アメリカで起こったエンロンの巨額粉飾事件が槍玉に上がり、世界の会計と監査のルールが厳格規制のために統一化されていく時代でもあり・・・企業の業績把握のための伝統的な会計基準が、金融商品のバリュエーション(評価)のための企業価値査定、将来キャッシュフロー予測のための道具に変わっていき、各国の会計基準が廃されて「国際会計基準(IFRS)」に収斂されていくというダイナミックな時代で、何もかもが変わっていくのでトレンドを追っかけ甲斐ある時代でした。
そんな中、日本のビッグ4(EY/新日本、KPMG/あずさ、Deloitte/トーマツ、PwC/あらた)のような大きな事務所は海外のマニュアルをそのまま使うようになり、一方で独立系事務所でだった所属事務所(双研社)では国際/海外のプラクティスを独自に調査して新たな手法を組み上げる必要に迫られ、それに嬉々として取り組んでいたのが当時の彼でした。
調査や情報収集のために国際会議に参加してきて、集めた素材をもとに監査のプログラムを組み上げてみたり、わからないことがあるとビッグ4の関係者と情報交換させてもらったりと、さまざまなフィールドワークをしながらの専門職研究者ライフを過ごしていました。

5. ブームに乗ってキラキラ期
この頃、彼はちょっとしたトレンドに乗ります。新たに会社法や金商法といった公開会社法制が成立し、アメリカの制度を真似た新しい監査制度(J-SOX)が始まることになり、上場会社や会計士業界は黒船襲来みたいにパニックになるんですね。
「これまでの日本のやり方が全て否定されて、新しい海外ものを学ばなければならない」みたいな極端な空気ができて戦々恐々とし始めたところに、そんな中ちょうどよく海外の動向を好き放題に調べていた彼は、一種の「事情通」扱いを受けて方々でセミナー講師に呼ばれるようにもなりました。
時代的には六本木ヒルズができて、ライブドアの堀江さんとフジテレビの日枝さんがニッポン放送の買収を巡ってバトルしてたり、そこに村上ファンドが出てきたりと資本市場が騒がしかった時代で、「会社は株主のもの」という株主資本主義が前面に出てきて、そのことと会計や監査の業界の変革はリンクしてもいて、自分のやっていることの文化的な意味を考えずにはいられない時期でした。
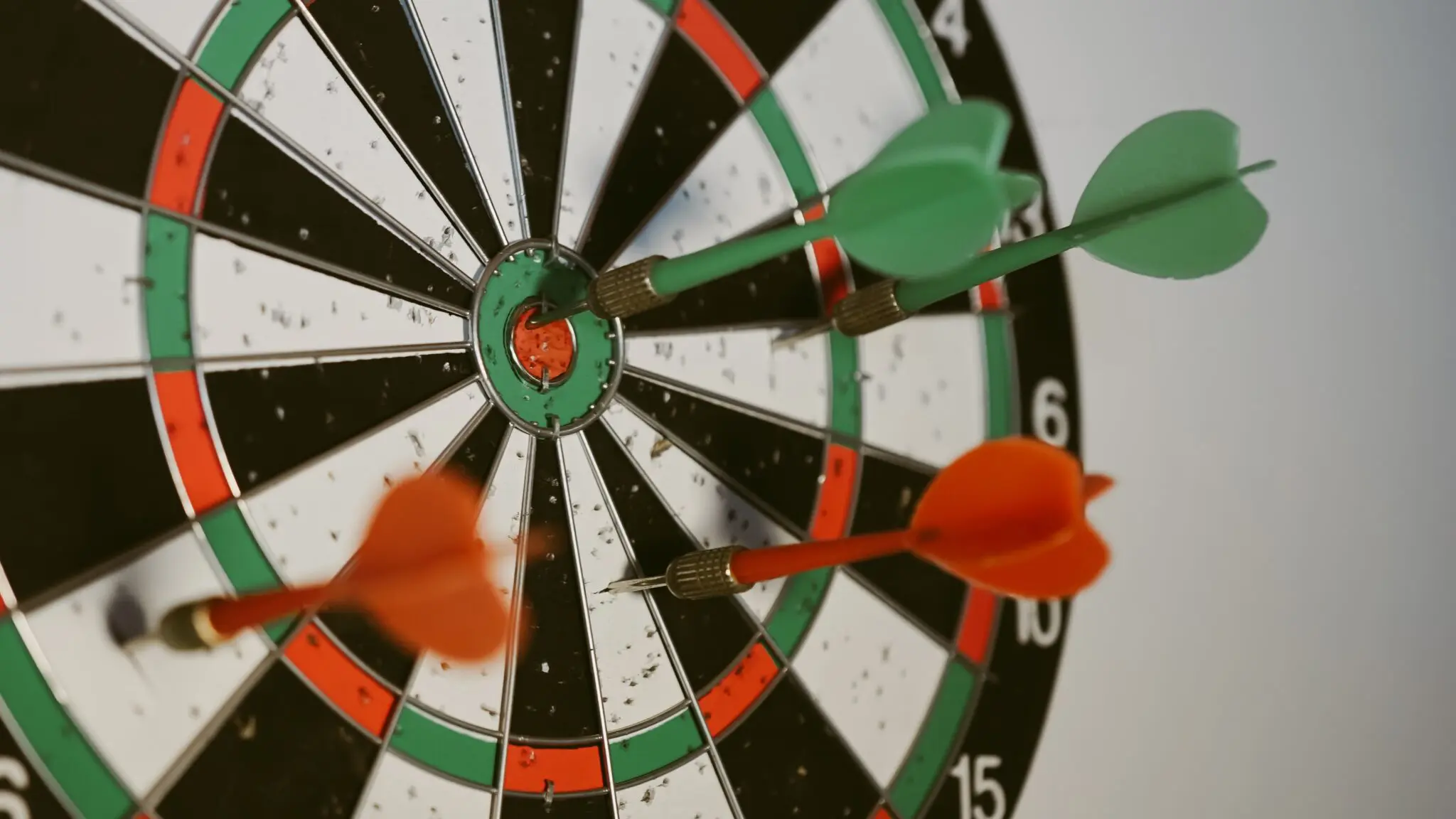
6. 仕事は何をしていたの?
そんな思索の傍らで、彼がしていた仕事はどんなものか。まず最初に勤務した監査法人時代の仕事のメインは、研究活動もしていましたが、もちろん「監査」でした。
彼が入った監査法人はちょっと変わっていて、「会計はビジネスの言語であって、決算書は会社がどのように自社の業績を捉えているかについての声明(ステートメント)である」という独特の思想(会計言語論)をもっていました。ジョージ・O・メイや青柳文司という学者さんの系譜に属し、時折そちら系の学者さんが事務所のサロンで話にくるというアカデミックな雰囲気で、ここで彼のプロフェッショナル観は育てられました。
会社のビジネスモデル、経営思想、戦略、プロセスやシステム、稼ぐ仕組みとそれを阻害する要因、それらが具体的な会計数値や業績トレンドに多層に現れるから、その意味を把握できるように十分に「企業活動の理解」をして、その感覚を持ちながら「決算数値の検証」をする、そんなで行うのが監査という活動であると。なかなか面白い見方でしょう?
そしてこの監査という仕事は、基本的に会社の人たちと話をしていくことで彼らから見える風景を聞き取っていくことと、それと会計情報、資料やデータを確認することの組み合わせでできています。ここで、彼が前者に関係して着目したのが「聞く技術」でした。

7. やがて、人間についての全方向的な学びへ
彼が日々を監査の現場で過ごす中で、気がついたことは、聞き方によって語られる物語は変わるということでした。ちょうど事務所のバックボーンになっている学者である青柳文司さんが「会計言語論から会計物語論へ」と理論を発展させ始めた時期でもあり、その影響も受けていたのかもしれません。実践家としては、それならそのもの物語にどう関与するのか、そのことを考えるようになっていきました。
そこで彼が出会ったのが、日本に入ってきたばかりの「コーチング」。今ではメジャーな領域ですが、当時はまだまだ黎明期。トレーニングに来る人もまだ裾野が広がっておらず、キャリアコンサルタント、組織開発のプロフェッショナル、大手企業の人事職など、非常に多彩かつ尖った人たちの集まりでした。自然と学びのコミュニティが形成され、情報交換がなされるなかにいることで、彼はさらに学びを広めていくことになりました。
アーノルド・ミンデルからプロセス・ワークやファシリテーションを学び、エコビレッジムーブメントに触れて英国のフィンドホーンにしばらく滞在し、アレクサンダー・テクニークを学びにニューメキシコへも。人間の振る舞いや状態に、深く影響を与え可能性のあるあらゆるものに触れていったという感じでした。中でもコーアクティブ・トレーニング・インスティチュートのコーチング及びリーダーシップのトレーニング、そしてコミュニティにおける交流からは非常に大きな影響を受けたように思います。

8. 広がった視野が新しい動きを生み出す
この「人の話をどう聞くか」から始まった旅路は、歩き始めると果てしない広がりを持っていました。そしてそんなふうに多様な風景を見続けるうちに、彼は監査の仕事にどこかで限界を感じるというか、飽きていくようになりました。そこには明確な仕事の目的や機能、終着点があって、その枠組みが徐々に窮屈になってきていたのです。
経験の中で広がった視野の中で、もっと積極的に社会の中で何かをしたいと思うようになり、やがて彼は監査法人での活動とは別に、自分の専門分野を基盤としてコンサルティングを行うようになりました。最初の顧客はコンサルティングファーム、やがてそれがIT業界に広がってゆくのですが、主としてコンサルタントを対象に、その先にいるお客さんを支援するための知識やノウハウを授けるという感じでした。
この時期の彼はアウトプットに励み、インプットも必要になって、様々な手法を学んだ時期でした。当初扱っていたテーマは、親しみのある会計や監査にまつわる領域(J-SOXやIFRS)でしたが、徐々にM&Aや事業価値評価といった時代性のあるテーマにも触れるようになりました。
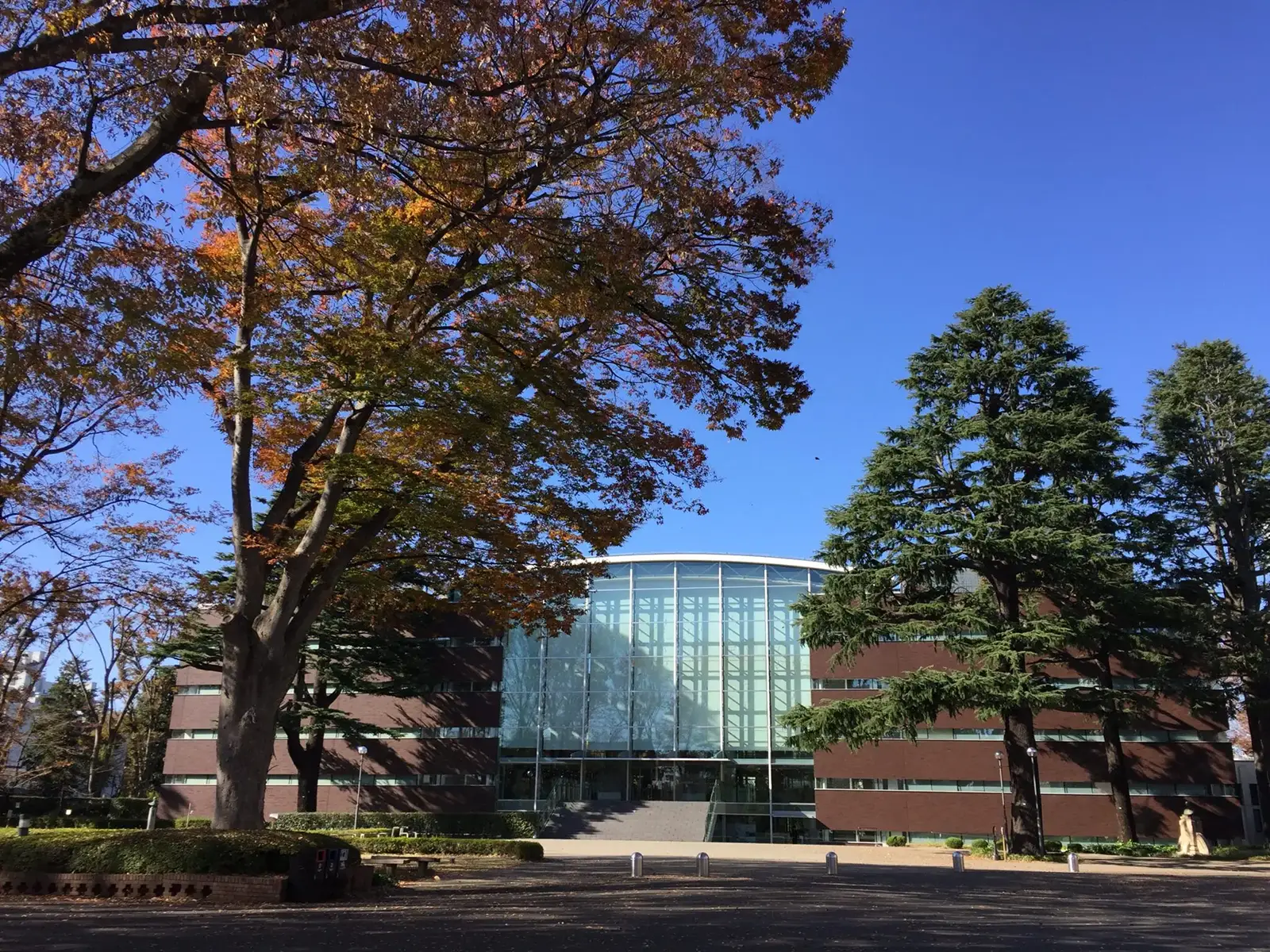
自習室で勉強ではなく、仕事ばかりしていたのをたまに教授に突っ込まれていました。
9. 「自分の仕事」を求めてロースクールへ
そんないろんなことに取り組みながら、彼はロースクールに行くんですよね。たくさんのことの並行生活だったわけですが、そのくらい思うところがあったんだと思います。自分が体験したり学んできたことのすべてをもって何かを創造すること、そのことによってまだ見ぬ誰かの役に立てる仕事を探すこと、そこにはアーティスト的な切実さがあったように思います。
当時は関与していた監査法人で他法人との統合が起こり、次々にやってくる新たな仕事やチャンスを一つ一つ形にする機会もあったり、友人が地方で立ち上げた環境系ソーシャルベンチャーにも関与したり、国際的なコンサルティングファームのM&Aや知財に関わる支援をすることもあったりと、多忙を極めてもいましたが、そのことこそ自己表現の場やスタイルを模索する活動そのものでもあったと思います。
この時期はいろいろと大変さもありましたが、2011年の入学からコツコツ勉強を続け、予備試験(2017)、司法試験(2018)、司法修習を経て弁護士となり(2019)、2020年に自分の法律事務所を開設することができました。
なお当初は会計士時代から慣れ親しんだ銀座/日本橋に事務所を置いていたのですが、コロナ下で司法手続もリモートシフトが進み、地方にいることがあまり不利でなくなるのを感じて、2022年に事務所を宇都宮へとローカルシフトしました。

10. 地方で展開していく人生
このシフトは結果としてうまく行ったなと思っています。これはとても感覚的なことなのですが、東京のような大都市にいると、たくさんのプレイヤーのいる経済システムの中でどのように選んでもらうかという視点になりがちで、どうしてもサービスや能力の優劣、つまり「機能」でクライアントと付き合うという側面が出てきやすくなる。これは彼の感覚でいうと「効率的だけどあまり人間的でない」感触があって。
ただ地方に行くと、そもそもプレイヤーが多くないので、一人一人の個人の存在感が重要になってくるし、ある程度クローズドなコミュニティの中で、自然とその個性と役割がマッチングされてくるような感覚があるのです。
先端的なことをやってきた会計士としてのキャリアが金融機関の監査や事業再生/M&Aといった分野とのつながりを生んでくるし、また、カウンセラーとしての気質やキャリアが、相続や信託といった高齢者・障がい者分野とのつながりを呼び込んでくるようなところがあって、結果として経験が積み上がって得意なことも生まれてくるようなところがあり。
また超高齢化社会へと向かう社会の中での事業承継や後見のようなテーマには時代性もあるし、また、実践技術的な要素も様々にあり、何かをコツコツ積み上げて極めようとする気質の彼にはぴったりだったりもして。おかげで気がついたら、それぞれの分野の日弁連の方の委員も務めることになって、いつかの会計士時代と同じような展開だなと思っていたりもします。

11. 個人の「終活」を支える弁護士として
自己紹介の最後に、まずは、最近弁護士として特に取り組んでいる分野の話を。
まず個人向けの領域としては、相続・後見・信託・尊厳死宣言・死後事務委任といった高齢者分野というか、もっと言えば人の「終活」にまつわる領域ですね。この文脈で親の話をするのもアレなのですが、実際問題として彼の年齢になると、両親がまさにこういったことに向き合う時期になるわけで、息子としてどんなふうにそれを手伝ってあげられるだろうか、と言うような視点で様々なことを考えながら取り組んでいます。
これは会計士時代とは、また全然違う分野ではあるのですけど、そうはいっても知識や技術を組み合わせて解決を導く部分は確実にあるし、目の前にいる人の想いを深く聞き取って対話をしていくと言う面では「人の話をどう聞くか」という、長らく追いかけてきたテーマとの直結することでもあって、とてもやりがいのある分野と出会ったなと思っています。
この分野を扱うと言うことは、誰かの「人生の終わり」に立ち会うと言うことでもあって、人生の後半に差し掛かった自分自身のこと、祖父母や両親のこと、あるいは次世代の子供たちのことを折に触れて考えるという経験もしています。いつぞや人間をめぐる幅広い探求をしたことが、この思索に深みを加えてくれてもいて、とてもありがたいなと思っています。

12. 事業者の「脱出」を仕掛ける弁護士として
そして会社向きというか、そうはいっても、経営者の方個人の支援という色合いも強いのですが、経営危機に陥っている企業の再生・倒産分野に最近は関わることが多くなってきています。
これは信条なのですが「事業や会社が人間のための営み」なのであって、「人間が事業や会社の道具や犠牲になることは、絶対にあってはならない」というスッキリと割り切られた感覚が基本にあるんですよね。なので、会計士時代に存分に培った幅広な知識と道具箱で、その窮状からどうやって相手が抜け出せるかを考え、その実行を支えることが大好きだったりします。結構スリリングな側面も多い分野だったりもするので・・・・
これは文化なのかもしれないんですけど、日本の経営者って真面目で責任感が強い方が多くて、もともとリスクがある事業の世界で負った債務を、自らの「責任」として肩の上に乗せっぱなしでずっと踏ん張っている方も多く。。。とはいえ人間全てをコントロールできるわけでは無いし、どうしようもない局面はあるはずで、そこで強調されるべきは自己責任論じゃないと思うんですよね。
なので法律を駆使して、事業の現状に見合ったところへ債務の金額を引き下げる破産法や民事再生法はとても良いなと。だって金融機関だって、経営者がリスクをとって事業運営をしていることは百も承知で、一定割合の企業はそういう結果になることは分かって商売してるんですから、こういうリセットボタンを機能させることってとても大事でもあるんですよね。
幸いなことに、このことは金融社会のコンセンサスにもなりつつあって「経営者保証ガイドライン」という企業が行き詰まった時の再生を後押しするような文書も公開されたりしていて、その実行環境は整いつつあるのです。とはいえまだ、特に地方では担い手になる専門職が少ないみたいなんですけどね。微力ながらその一角でいようと思っています。

13. 今日もまた、途上を歩いている
こうやって書いてくると、一体彼はどこに向かっているんだろう、という気がしますよね。ある日、両親からも「貪欲な努力家」と言われ、また「どうしてそんなに生き急ぐのか」と聞かれたことさえあります。何にドライブされているのかは、そう言われてみると、自分でもちょっと謎だなぁと彼は思っています。
「これが私の人生だ」みたいなテーマって、コーチング界隈ではすごい大事な主題だと言われるんですけど、彼は聞かれてもはっきり言えないような気がしてます。様々なところを旅して、風景に驚かされ、その時々に心に去来するものに出会っていく、強いていえば、そういうスタイルで生きることを大事にしているので。
それぞれの時におけるテーマはあっても、なかなか普遍的なテーマって見出し難いのです。全ては変わりゆくのが自然という感覚もあって、人生って何か積み上げていくことでは無いのかなという感じがするんですね(と言いつつ、知識やノウハウは明らかに極める方向に走っているのですが)。
ちなみに好きな人物を挙げると「イチローさん」だったりして、いや、あの人こそ一貫してきた人でしょうという評価かもしれないんですけど、彼からみるとイチローさんは「永遠の旅人」のように見えるんですよね。いつも何かの途上にいて、いつも進化を続けている。それを人は切り取って「大きな達成」だというかもしれないけれど、それは本人にとっては、そうではないのかもしれないなと、勝手に彼は想像していたりします。
お気軽にお問い合わせください
ご返答は平日10:00~17:00内での対応となります。
※メール受付は24時間365日しております。
お問い合わせいただいてから、通常3営業日以内にメールまたは、お電話、その他ご希望の方法にてご連絡させていただきます。
なお、お問い合わせ内容によっては、ご返答しかねる場合もあることについては事前にご承知おきください。